恒久的施設(PE)とは?
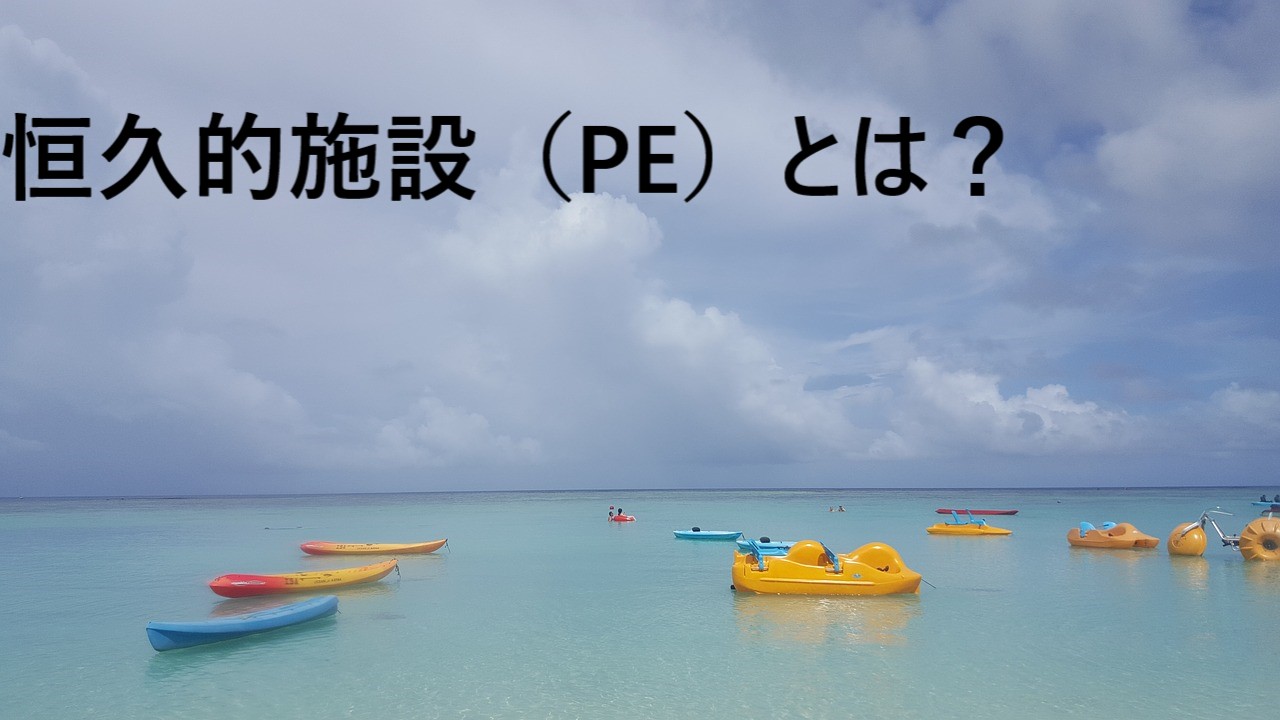
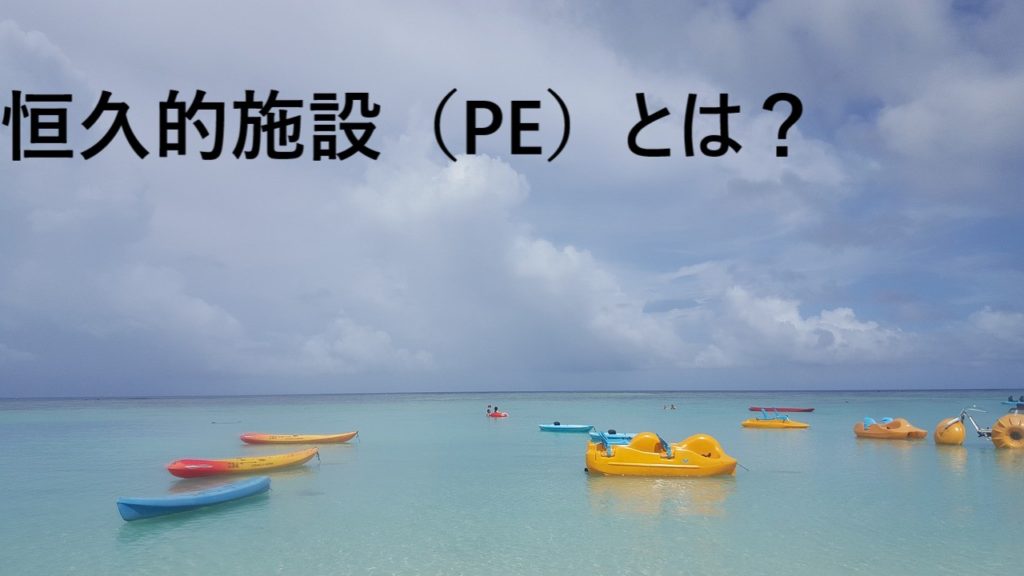
あまり耳にしたことない言葉「恒久的施設」。通称PE。
税務的にはPE課税なんて言葉あったりします。
今回は、ちょっと難しい話PEについてです。
目次
非居住者と外国法人の課税関係
PEを説明する前に、まずは非居住者と外国法人の課税関係の整理をします。
非居住者と外国法人に対する課税は「国内源泉所得」のみが課税対象とされ、この国内源泉所得でも、その支払いを受ける非居住者と外国法人の「恒久的施設」の有無によって課税関係が異なります。
国内源泉所得とは?
国内源泉所得とは、次のようなものです。
- 恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得
- 組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの
- 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価
- 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
- 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価
- 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、外国法人が発行する債券の利子のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
- 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
- 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
- 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
- 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの
- 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
- 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等
- 国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
- 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配
- その他の国内源泉所得
恒久的施設とは?
さて。ここから本題です。
「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」(Permanent Establishment)と略称されており、次の3つの種類に区分されています。
ただし、我が国が締結した租税条約において、国内法上の恒久的施設と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける非居住者等については、その租税条約上の恒久的施設を国内法上の恒久的施設とします。
(1) 非居住者等の国内にある事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場、作業場若しくは鉱山その他の天然資源を採取する場所又はその他事業を行う一定の場所。
(2) 非居住者等の国内にある建設、据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下「建設工事等」といいます。)で1年を超えて行う場所(1年を超えて行われる建設工事等を含みます。以下「長期建設工事現場等」といいます。)。
(3) 非居住者等が国内に置く代理人等で、その事業に関し、反復して契約を締結する権限を有し、又は契約締結のために反復して主要な役割を果たす者等の一定の者。
恒久的施設の有無で課税関係はどのように違うの?
例えば、「恒久的施設」を有する非居住者に対する使用料等の対価について、その対価が恒久的施設に帰せられる所得である場合は、原則として源泉徴収の上、総合課税の対象とされますが、その対価が恒久的施設に帰せられない所得である場合は、原則として源泉分離課税の対象とされます。また、「恒久的施設」を有しない非居住者に対する使用料等の対価については、源泉分離課税の対象とされます。
まとめ
実は、とっても難しい恒久的施設。
日本国内に恒久的施設を有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。
これが難解で。
国税に勤務している頃、なんど恒久的施設に該当するか否かで議論したことか。
昨今、海外の投資家が増えていますので、国税当局は頭を悩ませているんだろうなあ。
【編集後記】
信用って大事です。

